日本蜜蜂の給餌について調べていたところ、自作の転化糖液糖の給餌には思わぬ危険性があることが分かりました。副産物のHMF(ヒドロキシメチルフルフラール)という物質が生成される可能性と、そのリスクを踏まえた「蜜蜂に安全な給餌方法」について詳しく解説します。ハチミツ中のHMF濃度基準についても触れています。
関連YouTube動画も是非参考にしてください。
「ミツバチにその給餌は危険です!」
日本蜜蜂を飼育していると、給餌を行った方がよいと思うタイミングがはっきりとあります。代表例は、花の蜜が乏しくなる盛夏(蜜枯れ)と、越冬に向けて貯蜜を増やしたい秋です。何を与えるかが重要ですが、ネット上では「ショ糖水溶液にクエン酸を加えて加熱し、転化糖液糖にして与える」方法がよく紹介されています。しかしこの方法には落とし穴があります。酸と熱の条件下では、ショ糖が果糖とブドウ糖に分かれるだけでなく、同時にHMFという望ましくない副産物が生成されることが多いのです。良かれと思って手間をかけた給餌が、結果として群れを弱らせてしまうこともあります。本記事では、その仕組みと代替策を具体的に示します。
せっかく手間をかけたのに「ミツバチさん大迷惑!」とならないように、ぜひ本記事を参考にしてください。
この記事でわかること
- 自作の転化糖液糖が危険とされる理由を、反応の流れと観察できるサイン(色味の変化など)から理解できます。
- HMFとはどのような物質で、どのような条件で増えやすいのか、その基礎を把握できます。
- HMFが短期・中期・長期で蜜蜂に及ぼす影響がイメージできます。実験報告を引用しながら説明します。
- 趣味の養蜂で現実的に選べる「安全な給餌の方法」と、季節ごとの実践的なタイミング・手順が分かります。
糖の基礎知識
代表的な糖の種類
- ショ糖:英名はスクロースで、私たちが日常的に使う砂糖の主成分です。化学的には二糖類に分類され、果糖とブドウ糖が結合した構造を持ちます。
- 果糖:英名はフルクトースで、単糖類に分類されます。果物に多く含まれ、水に溶けやすく結晶化しにくい性質があるため、液糖の取り扱いを容易にします。
- ブドウ糖:英名はグルコースで、こちらも単糖類です。生物の主要なエネルギー源です。健康診断で測定される「血糖値」は血中グルコース濃度を指します。
花の蜜にはショ糖が比較的多く含まれますが、完成したハチミツでは果糖とブドウ糖が主成分になります。これは、ミツバチが持つインベルターゼという酵素が、採取した蜜のショ糖を果糖とブドウ糖に分解しているためです。人の消化でも同じように酵素の働きで分解が進みます。
転化糖液糖とは?
- 転化糖液糖とは、ショ糖を酸や酵素の力で分解し、果糖とブドウ糖へ「転化」させた液糖のことを指します。歴史的には旋光度の「反転(invert)」が名称の由来です。
- 清涼飲料の原料として知られる「果糖ブドウ糖液糖」も同じ系統の製品で、こちらはデンプンを原料に作られる点が特徴です。
- 果糖を多く含むため結晶化しにくく、取り扱いが容易に感じられることと、ハチミツに似た糖構成であることから、養蜂でも魅力的に見えることがあります。
転化糖液糖は一見便利ですが、家庭で「酸+加熱」によって作る方法はHMF生成のリスクが避けられない点に注意が必要です。見た目がうっすら黄ばむ、あるいは薄い琥珀色に変化するなどのサインが現れた場合は、反応が進み過ぎた可能性が高いです。
HMFとは?
発生の仕組み
- 酸性条件下で加熱すると、ショ糖はまず果糖とブドウ糖に分かれます。そこで終われば良いのですが、果糖はさらに脱水反応を段階的に受け、5-ヒドロキシメチルフルフラール(HMF)へと変化します。
- HMF自体は無色ですが、並行してカラメル化に伴う着色物質や褐色ポリマーが生じるため、液糖が黄〜琥珀色を帯びることがあります。色の変化はHMFが増えている可能性を示す“目安”になります。
HMF濃度の目安
- ほんのりした黄ばみは、経験則的に30〜60 ppm程度のHMFが生じている可能性を示すことがあります。
- 薄い琥珀色まで進むと、60〜100 ppm以上に達しているケースが想定されます。
- クエン酸の量や加熱時間・温度が高いと、200 ppmを超えるレベルに達したという報告もあります。
家庭環境でHMF濃度を正確に測定するのは現実的ではありません。つまり「見た目で薄い色だから大丈夫」とは言い切れず、知らぬ間に高濃度のHMFを含む液糖を作ってしまうリスクが残ります。
HMFが蜜蜂に与える影響
論文などを検索して調べた結果を以下に示します(本記事の最後の引用を参照ください。)
- 短期(数週間)の影響:おおよそ150 ppm近辺の濃度で、実験条件下では半数死亡が観察されたという古典的研究があります。短期間でも致死的に働く可能性は無視できません。
- 中期(約3か月)の影響:250 ppm付近では寿命の短縮、消化管(中腸)上皮のダメージ、下痢の発生、採餌量の低下など、群れの健全性を損なう変化が報告されています。
- 長期(越冬期)の影響:40〜50 ppm程度という一見低めの濃度でも、毎日少量ずつ摂取し続けると群勢がじわじわ落ちると評価されています。越冬中に弱っていく群の背景要因として、HMFの慢性的な摂取が疑われるケースも考えられます。
以上を踏まえると、自作の転化糖液糖を安易に与えることは、群れの短期・長期の健康リスクを高める行為になりえます。
ハチミツ中のHMFについて
- 国際基準(CodexやEU)では、特別なハチミツを除きHMFは40 ppm以下が求められます。
- 日本では全国はちみつ公正取引協議会の基準で、50〜59 ppm以下とされています。
- 高HMFの液糖を給餌した状態で採蜜すると、完成したハチミツのHMFが基準を超えてしまう恐れがあります。たとえば100 ppmの液糖が花蜜と1:1で利用され、その後の濃縮でHMFが相対的に上がれば、完成品が基準値をオーバーする可能性は十分にあります。
なお、HMFはコーヒーなど広く食品に含まれ、人への影響について明確な有害性は明確には示されていません。しかし「蜜蜂の健康」と「採蜜したハチミツの基準への適合」という、養蜂として重要な2点の観点からは、HMFの混入は可能な限り避けるべきです。採蜜時期の設計で混入リスクを下げる(夏に与えたら秋には採蜜しない、秋〜冬に与えたら春の採蜜前に貯蜜を使い切らせる等)工夫も有効です。
安全な給餌方法
避けるべき方法
- クエン酸を加えて煮沸し、家庭で転化糖液糖を作る方法は避けます。見た目は透明に近くても、HMFが実際どの程度含まれているのかを家庭で把握することは困難です。
現実的な選択肢
ショ糖水溶液(砂糖水)
- ショ糖水溶液を給餌することが現実解と考えます。
- 夏の基本配合は「白砂糖1 kg+お湯1 L」です。流動性が高く、蜜源不足の緊急補填として扱いやすい濃度です。
- 秋の基本配合は「白砂糖2 kg+お湯1 L」です。濃いめにして貯蜜づくりを後押しします。
- 作り方の要点は「70℃以下で溶かす」「沸騰させない」「作り置きを避け、早めに使い切る」の3点です。例えば、1 Lの水を60〜70℃に温め、白砂糖をよく攪拌して完全に溶かしてから与えます。低温で溶かすことでHMFの生成を実質的に抑えられます。
- 嗜好性を上げたい場合は、少量のハチミツを香り付け程度に混ぜる方法もあります。ただし病原体伝播リスクを考慮し、品質と信頼性には十分注意する方が良いでしょう。
その他の方法
- 国産ハチミツを給餌に用いる方法は、越冬後半などで群れが不調の際に効果的に働くことがあります。一方でコストが高く、ハチミツを介した病気の伝搬リスクも否定できません。外国産の安いハチミツはお勧めしません。
- 海外製の「低HMF転化糖液糖」は理論上は有望ですが、日本国内で趣味規模に適したロットを安定入手するのは難しく、現状では現実解になりにくいのが実情です。
- 酵素(インベルターゼ)を入手して自作で低HMF化を目指す手段もありますが、こちらも個人の入手性や品質管理のハードルが高く、再現性を保つのが難点です。
給餌のタイミングと方法
- 夏の蜜源不足時は、群れの消滅を防ぐ目的で限定的に給餌を行います。自然蜜源が回復したら速やかに中止し、外部からの糖の混入が採蜜期に及ばないよう配慮します。
- 秋の越冬準備では、十分な貯蜜を確保させるため、濃いめのショ糖水を計画的に与えます。採蜜の予定がある場合は、時期をずらすなどして混入を避けます。
給餌の工夫
- 匂いによる盗蜜やアリの誘引を避けるため、給餌器は巣箱内部(可能ならスノコ上)に設置します。夕方に設置し、翌朝には確実に回収する運用が有効です。
- 蜜蜂が溺れない構造の給餌器を使うことが必要です。蜜蜂は結構簡単に溺れます。
冬の給餌について
- 冬季は水分の多い液糖が不向きとされます。低温下では蜜蜂が水分をうまく処理できず、巣内の湿気や冷えを助長する恐れがあるためです。
- 必要な場合は、ショ糖自体を固形で与える、少量の水で練ってペースト状にする、あるいはキャンディーボード状に加工するなど、水分を抑えた形態での補助を検討します。
まとめ
- 家庭でクエン酸+加熱により作る転化糖液糖は、条件次第で高濃度のHMFを含みやすく、短期的には致死、長期的には群勢低下など、蜜蜂に明確な悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 趣味の養蜂で安全性と再現性を両立する現実的な選択肢は、適切な温度管理で作る「ショ糖水溶液(砂糖水)」です。
- 給餌は「夏の蜜枯れ時」と「秋の越冬準備」を中心に、夕方に内部給餌で与えて翌朝回収する運用を徹底し、採蜜期への混入と盗蜜リスクを抑えます。
FAQ
- 自作の転化糖液糖は日本蜜蜂にとって安全ですか?
-
クエン酸を入れて加熱する自作の転化糖液糖は、HMF(5-ヒドロキシメチルフルフラール)が高濃度になりやすく、日本蜜蜂の短期の死亡や長期の群勢低下リスクがあります。趣味の養蜂では「安全とは言えない給餌方法」と考え、基本的に避けるのが無難です。
- HMF(5-ヒドロキシメチルフルフラール)とは何ですか?日本蜜蜂にどのくらい危険なのですか?
-
HMFは果糖が酸+加熱で分解するときにできる副産物で、砂糖水や転化糖液糖の加熱で増えます。150ppm前後で半数死亡の報告があり、40〜50ppmのような一見低い濃度でも長期摂取で群勢低下が指摘されており、「少しなら大丈夫」とは言い切れません。
- 日本蜜蜂に安全な給餌方法(レシピ)は何ですか?
-
現実的で安全性の高い選択肢は、クエン酸を入れないショ糖水溶液(砂糖水)です。夏は「白砂糖1kg+お湯1L」、秋は「白砂糖2kg+お湯1L」を目安にし、60〜70℃くらいで溶かして沸騰させないことでHMFの生成を抑えます。
- 日本蜜蜂への給餌のベストタイミングはいつですか?
-
給餌が必要になる主なタイミングは「盛夏の蜜枯れ時」と「秋の越冬準備」です。採蜜するハチミツに砂糖由来の糖が混ざらないように、給餌する時期と採蜜時期をずらすなど、日本蜜蜂の健康とハチミツの収穫タイミングを意識してスケジュールを組みます。
- 冬の給餌や盗蜜対策では何に気をつければいいですか?
-
冬は水分の多い液糖は巣内を冷やしやすく、日本蜜蜂には不向きです。必要なら固形砂糖やキャンディーボードなど水分の少ない形で与えます。また、盗蜜対策としては「巣箱内部での給餌」「夕方に設置して翌朝回収」「巣門や巣箱外に糖液をこぼさない」ことがポイントです。
参考文献
本記事を作成するのにあたって参考にした資料やサイトは以下です:
・クエン酸の量や加熱時間によっては、200ppmを越えるHMFが生成されることがある。
・短期、およそ2〜3週間のスパンでは、150ppm前後で半数死亡が出たという1975年の古典的試験がある。
・HMFが250ppmあたりまで上がると、平均寿命が大きく縮み、中腸の上皮が傷んで下痢、採餌量が落ちるといった変化も見られるとの2020年の論文がある。
https://www.mdpi.com/1424-2818/12/1/18?utm_source=chatgpt.com
・長期、90日〜越冬のスパンでは、40〜50ppm程度でも日々の微量摂取が積み上がって群勢がじわじわ落ちると評価されている。
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7227
・アメリカの養蜂業界の実務ガイドでは給餌する場合のHMF濃度は30 ppm 以下とすることが推奨されている。
・国際食品規格やヨーロッパの基準では、特別なハチミツを除き、HMFは40 ppm以下が基準となっている。
・Codex(CXS 12-1981)
・EU 指令 2001/110/EC(Annex II)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32001L0110&utm_source=chatgpt.com
・日本では全国はちみつ公正取引協議会により50ppmまたは59 ppm以下が基準となっている。
参考記事
ニホンミツバチ飼育全般について以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。

終わりに
ここまで読んでくださりありがとうございました。この記事が少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
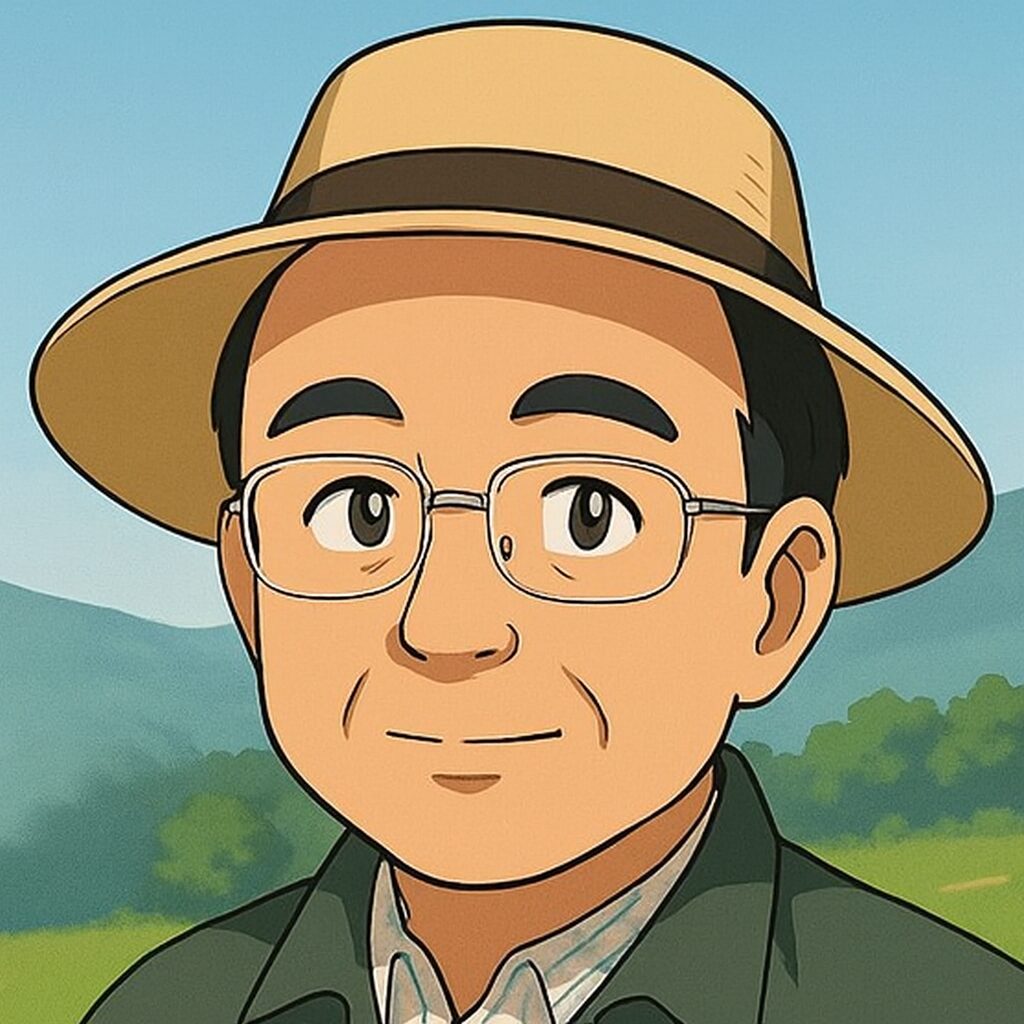


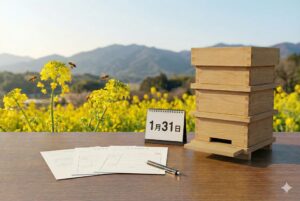

コメント